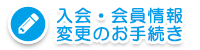藤原保明先生
藤原保明先生  会場の様子
会場の様子 茗渓会の公開講座は、9月14日(土)茗渓会館で開かれました。今回は、「シリーズ藤原教授の英語の話 第7弾」として、筑波大学名誉教授、聖徳大学文学部長である藤原保明先生の「地名と人名から探る英語圏の文化」と題するお話でした。約60人の参加者の熱心な聴講の中で、お話は淡々と進められました。
藤原先生は、「人名や地名には、言語・民族・時代・文化など、さまざまな情報が埋め込まれている」として、地名に秘められた情報を、古英語に遡って解きほぐしていかれました。ブリテンという地名の由来、イングランドが「アングル人の国」の意味であることを古英語から明らかにされます。さらに、「ダービー」が「鹿がいる村」の意味であるとか、「ランカスター」は古英語からみると「ルネ川のほとりの砦」である、などなど、日本人になじみのある地名を取り上げてその由来を次々に明らかにされていきました。
人名でも、語尾に「man」がつくチャップマンや「son」がつくアムンゼン、アンデルセンなどたくさんの例により、父祖名継承の語尾を分析しました。英語では男の名前に「剣」とか「槍」といった戦争における戦功を語る命名があるが、実は女性にも「ヒルデブルフ」(戦闘+砦)などの名前があることは、参加者を驚かせました。
最後に、日本人の命名法と英語圏における命名法を比較して、農業の文化と狩猟や牧畜の文化圏の違いを浮き張りにされるお話しで締めくくられました。
参加者からは、「高度の学問の話を、こういう機会を持って聞かせていただいたことは有り難いことです」というご意見や、「これまでの講演録と資料を茗渓会のホームページに載せてほしい」という意見などたくさんの感想を頂きました。
講演録
今回の講演では英語と日本語の人名と地名に込められた言語・民族・時代・文化などの情報を解きほぐしてみた。
1 イギリスの地名とその由来
イギリスという名称はポルトガル語のInglesに由来し、正式には「大ブリテン島および北アイルランド連合王国」、略称は「連合王国」である。イギリスを構成する諸島の中心は大ブリテン島(Great Britain)であり、イングランド、ウェールズ、スコットランドという3つの国を含む。ブリテンという名称はケルト系の先住民のブリトン人(Briton)に由来し、イングランドと「英語」のEnglishはゲルマン系のアングル族(Angles)に基づく。
イギリスの主な地名のうち、ロンドン(London)の語源には諸説あるが、「勇敢な」を意味するラテン語のLondinos(人名また部族名)が有力である。テムズ川 は「暗い」の意のサンスクリット語のtamasa に由来する。オックスフォード(Oxford)は「雄牛+浅瀬」という語構成である。ケンブリッジは古英語ではGrantebrycg(「泥川」(grante)+「橋」(brycg))であったが、その後、音も綴りも変化し、現在に至る。
ダービー(Derby)やラグビー(Rugby)などの語尾‐byは村や野原を意味する北欧語の古形に由来し、ヴァイキングが定住したブリテン島の北東部に多い。アングロサクソン系の人々の住む地域では、Gainsborough, Peterborough, Canterbury, Salisburyなどのように、この語尾は‐boroughまたは‐buryとなっている。
観光の名所 コッツウォルズ(Cotswolds)は古英語の Codeswald「コード(人名)の森」に由来する。「ランカスター」(Lancaster)は古英語の Lonceaster「ルネ川の畔の砦」までさかのぼれる。「ドンカスター」(Doncaster)のDon‐は「ドナウ川」(Danube)や「ドン川」(Don)と同様、サンスクリット語の danu ‘rain, moisture’ に由来する。一方、「ランカスター」の‐casterは南に下るとDorchester, Manchester, Winchesterのように‐chesterに変化し、さらにGloucester, Leicester, Worcesterのように‐cesterへと変る。なお、ManchesterのMan‐は古英語のmam ‘hill, breast’、WorcesterのWor‐は古英語のWigra(<Wigoran「ウィゴラ族の」)までさかのぼれる。2 アメリカの地名とその由来
「アメリカ」は新大陸に3度渡航したイタリアの商人アメリゴ・ヴェスプッチにちなんでドイツの地図製作者が命名したことに由来する。
米国の首都ワシントン(Washington)は古英語のWassingatun「ワッサ族(Wassa)の農場」に由来する。語尾‐ingは民族・父祖・地名を表し、Fleming, Stirling, Wappingなどの人名・地名に残る。一方、語尾‐tonは古英語ではtun[tu n]’enclosure, village’であり、現在はtownとなっている。‐tonで終る語はClinton, Edmonton, Eton, Hampton, Hilton, Merton, Newton, Norton など、多くの地名・人名に見られる。‐ington(=‐ing+ton)で終る地名にはKensington, Paddington, Wellington などがある。
アメリカにはNew York, New Jersey, New OrleansのようにNewがつく地名が多いが、これはイギリス人移住者の新大陸に対する期待の表れである。Yorkは古ノルド語の Iork ‘boar’ に由来するが、ウェールズ語の eburos ‘yew’「櫟(いちい)」に発する。ちなみに、Yorkはブリテン島の中間に位置し、かつてヴァイキングが移住し、王国を築いた所である。
Bostonは中英語のBotuluesto(u)n(=St. Botolf’s town「聖ボトルフの村」)に由来する。ロサンゼルス(Los Angeles)はスペイン語のlos Angeles ‘the Angeles’に発するが、本来は聖母マリアを称えた命名であった。 一方、シアトル(Seattle)はインディアンの酋長See‐yatにちなむ。
このように、英米の地名の元に人名があり、地名は人名に転用されることが多い。3 日本語の地名と数字
漢数字を用いた日本の地名は多いが、「一、四、九」は古い地名には用いられない。音読みの「四」は「死」、「九」は「苦」を連想するため避けられたであろうが、訓読みの「一(ひと)」が用いられない理由は不明である。「四谷」や音読みの「四十九(しじゅうく)」は新しい地名であろう。
「二田(ふただ)」、「二見」、「二俣」など、「二」はすべて訓読みである。音読みは「二色(にしき)」と「二宝(にほ)」があるが、前者では「丹(に)」、後者では「邇保(にほ)」など、数通りの表記や解釈がある。漢数字の「二」(に)を借りたのかも知れない。
「三」は「三角(みすみ)」、「三島(みしま)」、「三谷(みたに)」など、最も例が多いが、いずれも訓読みである。
「五」は訓読みの「五公(いきみ)」のみであるが、「いき(池)+み(あたり)」という説は漢数字の借用を窺わせる。
「六」は訓読みの「六名(むつな)」と「六座(むつくら)」の2例だけである。
「七」は「七崎(ななさき)」と「七美(しつみ)」の2例だけであり、後者は「しつ(垂)+み(廻)=傾斜地のあたり」の意味である。「七」の音読みを「しつ」に当てたのか。
「八」は「三」についで多く、20例のうち19例では「八木」、「八部(やたべ)」、「八代」のように訓読みである。「八太」(はた)は「幡多、波太、八多」などと同様、「八」の音読みの「は(ち)」を利用したのか。
「十」は訓読みの「十市(とをち)」だけである。
「十」より多い数字のうち、「百」は「百済(くだら)」だけである。この地名は百済からの帰化人が多く住んでいたことにちなむ。語源は「く(大)+たら(村落)」など諸説があるが、いずれも「百」を数字とみなしていない。「千」は訓読みの「千葉、千曲、千俣」など9例がある。「千栗(ちりく)」は「ちくり」が音位転換したもの。「千太」は訓読みの「ちた」と、音読みの「せむ(山が迫る)+た(処(ところ))」とみなす説が競合している。
古代日本の地名のうち、漢数字で表記されているものはほとんど訓読みであるが、数字に意味はなく、表音上漢数字を借りている例が多い。音読みの場合にも同様の例が若干ある。4 英語の命名の特徴
英語には Coleman(<炭坑夫)、Edelman(<高貴な人)、Goldman(<金取引職人)、Newman(<新来者)、Trueman(<信頼できる人)、Wellman(<泉のそばの住人)、Whiteman(<白髪・顔色の悪い人)、Wiseman(<賢い人)のように、 ‐man「~の人」を第2要素とする名前がかなり多いが、いずれも職業やあだ名に由来する。
一方、父祖名を継承した「~の息子」を表す語尾はいくつかある。アングロサクソン系の‐ingはFleming「フランドル地方の人」、Havering「へーブリング」のように地名か人名を表す。‐sonも同様に「~の息子」を表し、古ノルド語のsunr「息子」に由来する。例はAnderson, Edison, Emerson, Erikson, Harrison, Hudson, Jackson, Jefferson, Johnson, Lawson, Madison, Nelson, Parkinson, Richardson, Robertson, Robinson, Stephenson, Tennyson, Watson, Wilsonなど実に多く、地名になっているものもある。ちなみに、この語尾は北欧ではAmundsen, Andersen, Hansen(Hansの息子)のように‐senとなっている。
アイルランド語では「~の息子」はO’‐という接頭辞で表し、O’Brien, O’Connor, O’Donovan, O’Flaherty, O’Grady, O’Hara, O’Kelly, O’Leary, O’Neil, O’Reilly, O’Sullivan, O’Tooleなど、例はかなり多い。
Mac‐, Mc‐ はM(a)cDonald, MacArthur, MacBeth, McCartney, McGovern, McIntosh, Mackenzieなど、「~の息子」を表すスコットランドやアイルランド系の人名に多い。5 英語の命名の歴史
英語をさかのぼると、命名の特徴や原則が現代と異なってくる。8世紀初頭に成立した叙事詩『べーオウルフ』の登場人物の場合、男の名前ではEcg‐laf「エッジラーフ」(剣+遺物)、Gar‐mund「ガールムンド」(槍+手)、Oht‐here「オーホトヘレ」(追跡+軍隊)、Scyld「シュルド」(楯)のように武器や戦の名で構成されている場合が多いが、女の名前の Frea‐waru「フレーアワル」(支配者+配慮)やHygd「ヒュイド」(配慮)には女らしい優しさが込められている。しかし、他の構成素は男の場合と変わらず、Hilde‐burh「ヒルデブルフ」は「戦闘の砦」を表す。
991年に港町モールドンでデーン人と戦って敗れた太守の非業の死を悼んで書かれた古英詩『モールドンの戦い』の場合、30余名の武人の名のうち、Gadde「ガッデ」やMaccus「マックス」などの単純語の原義は不明であるが、Alfhere「身軽な戦士」、Alfnoth「小柄の勇者」、Athelred「高貴な力持ち」、Athelric「高貴な兵」、Byrhthelm「輝く守護者」、Byrhtnoth「眩しい勇者」などの複合語の場合、キリスト教の伝来 (597年)から400年近く経っているが、当時の武人の名前にはその影響は全く見られず、むしろゲルマン古来の命名の特徴が色濃く表れている。また、名前から武人たちの位が高かったことがわかる。
ゲルマン民族の伝統的な命名の特徴は頭韻にあり、ブリテン島に移住したジュート族の武将HengistとHorsaの兄弟や、『べーオウルフ』に登場するHealfdeneの息子Heorogar、Hrothgar、Halgaのように、子は親の名と同じ子音で始まる。
5世紀末にイギリスにキリスト教が伝わると、聖書に登場する名前が好まれるようになり、男の名前では、Abraham, John, Paul, Peterなどの預言者や聖人の名前、女の名前では、Ann, Catherine, Elizabeth, Maryなどが好まれるようになった。
英語圏の命名は職業やあだ名だけではなく、父祖名を継承したものが多いが、数字はほとんど無縁である。6 日本語の命名法
小規模で子沢山の農家が大半であったかつての日本の農村地域では、田畑を子どもに分配すると生計が維持できなくなるため、次男以下は他家に婿入りして、そこの家業を継ぐか、独立して会社や公の機関に勤めるかを選択せざるをえなかった。このような状況では、男子の名前の数字は家督相続の順序を示し、地域社会にとっても好都合であったのであろう。このことは命名の特徴として表れていて、男の子には順序を示す数字が好まれた。漢数字は一郎、三郎、五郎、八郎、一夫、三夫のように、最初に用いられる場合が多いが、勇一、信三、伝八、美千夫のように二番目となることもある。正雄、正男などの「正」、次男、次郎などの「次」は数字ではないが、一番目、二番目を表す。
一方、女子の命名にも漢数字は用いられるが、一子、二美、三三子、二三子、八重子のように第一要素に限られ、第二要素には用いられない。かつては、農村を中心に、大切な動植物である稲や牛、強い動物である熊、虎、龍、あるいは吉祥や長寿の願いを込めた「亀」、「鶴」、「朱鷺」にちなむ命名が多かったが、最近はこのような命名はすたれている。むしろ、「三貴、七海、百々子、千尋」など、口調や響きの良い漢数字が選ばれる。7 まとめ
狩猟や牧畜中心のヨーロッパでは、牧草地や森林の分割相続や長男に限った遺産の分配は慣習とはならなかったことから、男子の名前に出生順を示す必要もなく、命名には数字はほとんど用いられない。もっとも、父系中心の社会を反映して、父祖名を継承した姓は広く用いられている。また、地名に人名や部族名が深く関係していることが多いことも大きな特徴である。一方、日本語の場合、地名と命名に数字が密接に関わっている点は欧米と大きく異なる。
講演後の質疑応答も活発で楽しいひと時であった。